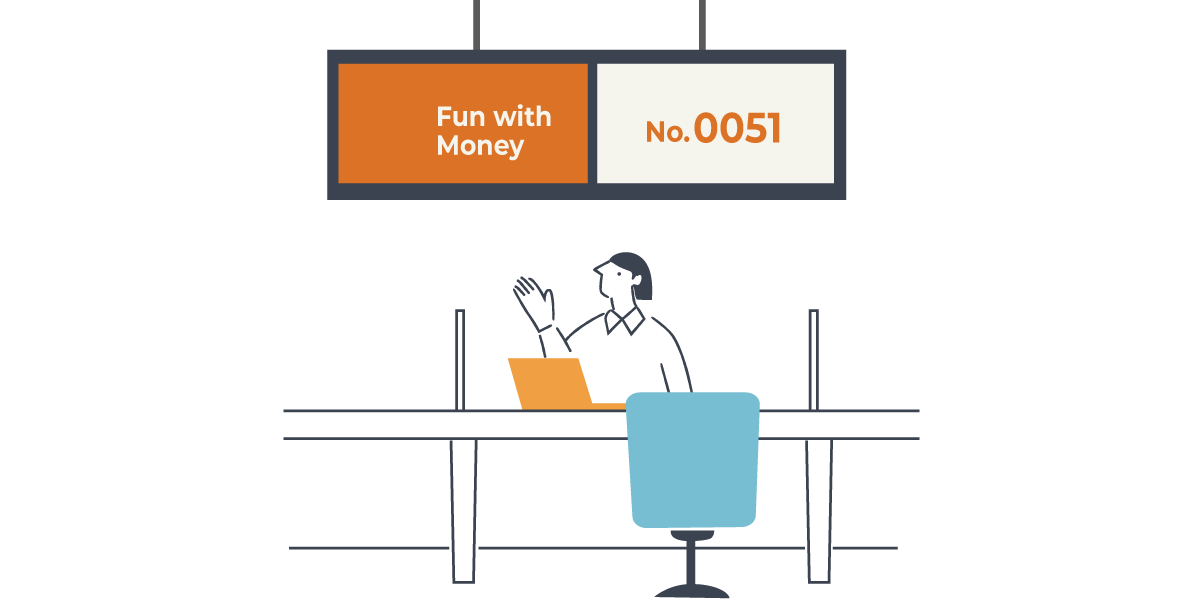SNSやWEB広告だけでは想定した成果が出せない昨今、学生の日常空間でブランドを自然に届ける「大学広告」が注目されています。学食モニター・購買モニター・ラウンジモニターを活用すれば、採用・商品訴求・地域ブランディングまで多彩な目的に対応可能。デジタルとリアルを融合させた次世代のキャンパスプロモーションを紹介します。
SNSやWEB広告だけでは想定した成果が出せない昨今、学生の日常空間でブランドを自然に届ける「大学広告」が注目されています。学食モニター・購買モニター・ラウンジモニターを活用すれば、採用・商品訴求・地域ブランディングまで多彩な目的に対応可能。デジタルとリアルを融合させた次世代のキャンパスプロモーションを紹介します。
■ はじめに:大学広告が注目されるデジタル時代の背景
SNS広告やWEBマーケティングは今や企業の標準施策となりましたが、同時に「情報過多」「広告疲れ」という課題も顕著になっています。特にZ世代の学生たちは、広告を“スキップ”するスキルを自然に身につけており、企業が思うほどメッセージは届いていません。
そんな中、企業のマーケティング担当者や採用広報担当者が再注目しているのが、大学広告です。
大学キャンパスというリアルな生活空間において、学生が日常的に目にする場所——学食、購買、ラウンジ——に広告を掲出することで、自然に情報を届け、ブランド体験を生み出すことが可能です。
オンラインでは得られない「信頼」「共感」「記憶への定着」が、この大学広告の最大の価値と言えるでしょう。
________________________________________
■ 大学広告とは? 学生の生活導線に寄り添うリアルメディア
大学広告とは、大学構内に設置されたデジタルサイネージやモニターを活用し、学生へ直接的かつ継続的にメッセージを届ける広告媒体です。学生は講義・昼食・購買・休憩といった日常動線の中で、自然にモニター広告に触れるため、広告の存在を押し付けがましく感じることがありません。
大学広告は「一度きりの接触」ではなく、「日常に溶け込む反復訴求」が可能な点が特徴です。
また、長田広告の「キャンパスメディア」では、大学内の主要拠点に配置された学食モニター・購買モニター・ラウンジモニターの3媒体を中心に展開。静止画・動画・音声を組み合わせた訴求が可能で、学生がスマートフォンを見ていない瞬間にもブランドに触れることができます。
________________________________________
■学生集客に効果的な大学広告の種類
学食・購買・ラウンジといった学生の生活導線上に設置された「大学モニター広告」に焦点を当て、各媒体の特徴と効果的な活用事例をご紹介します。学生に自然に届く、効果的な大学広告戦略のヒントを見つけてください。
1. 学食モニター:学生の最も長い滞在時間にリーチ
学食は、大学内で最も多くの学生が集まる場所のひとつです。
授業と授業の合間、友人とのランチ、サークル活動前後など、多くの学生が一定時間を過ごすため、視聴率・記憶定着率ともに極めて高い媒体です。
モニターは学生が着席した正面や、配膳カウンター近くに設置されているため、視認性が高く、長尺動画でもストレスなく視聴されます。
食品・飲料メーカー、アパレルブランド、企業採用PRなど、多様な業種で導入が進んでおり、特に採用動画では「企業の雰囲気が伝わる」と学生からの反応が高い傾向にあります。たとえばある企業では、学食モニターでインターンシップ動画を放映。QRコードを設けたことで、エントリー数が従来比で1.7倍に増加しました。
2.購買モニター:購買意欲の高い瞬間に広告を届ける
大学生協の購買スペースは、学生が日用品や文房具、食品を購入する場所であり、常に高い来店頻度があります。購買モニターは、まさに「行動直前」に広告を見てもらえる貴重な接点です。
購買行動と広告が直結するため、新商品の認知・購買促進・キャンペーン告知に非常に効果的です。
特に女性学生向けコスメや飲料、スナック菓子などのプロモーションでは、視認後すぐの購買行動が発生しやすい傾向があります。さらに、QRコードやSNSハッシュタグと連動したキャンペーンを実施すれば、オンライン拡散との相乗効果も期待できます。
リアルとデジタルを結びつける「O2Oマーケティング」の起点としても、購買モニターは注目されています。
3.ラウンジモニター:ブランドストーリーを静かに伝える空間
ラウンジモニターは、学生が休憩や談話、勉強を行う共有スペースに設置されています。ここでは学生がリラックスして過ごしているため、ブランドストーリーをゆったりと伝えるのに最適です。
採用広報動画、企業メッセージ、地域連携プロジェクト紹介など、“信頼感”を重視する広告には特に効果を発揮します。
長田広告では、複数大学を横断して放映できるネットワーク配信も可能で、エリア別・大学別にターゲティングした展開ができます。
________________________________________
■ 大学広告が選ばれる理由とメリット
1. 信頼性のある環境での広告接触
大学という教育機関内での掲出は、公的かつ健全な印象を与え、学生に安心感を与えます。企業イメージを損なうことなく、ブランド価値を高めることができます。
2. 繰り返し接触による高い記憶効果
授業・昼食・休憩など、1日に何度も同じ場所を通る学生に繰り返し接触できるため、潜在記憶への定着が促進されます。
3. 大学別・地域別にターゲティング可能
全国の大学ネットワークを活用し、採用エリア・商圏・ブランド対象層に合わせた出稿が可能です。
地域企業の広報や地元採用にも最適です。
4. デジタル×リアルのシナジー
動画・QRコード・SNS連携によって、キャンパス内の広告がそのままオンライン行動につながります。広告効果を数値化できる点も魅力です。
________________________________________
■データで見る大学広告の効果
長田広告独自のWEBアンケート調査ではありますが、デジタルサイネージが設置されている大学では、87.43%の学生がサイネージを認識して視聴していると回答。
(ほぼ毎日視聴21.52% ・週に数回視聴40.78%・月に数回視聴25.14%)
そのうち、22.87%がWEBサイトにアクセスした、21.28%は友人と情報共有をした、11.17%は大学のキャリアセンターや支援課に相談に行った、10.64%は採用説明会やインターンシップに申しこんだ、と回答を頂いております。
“学生から企業を見つけてもらう”という新しい採用スタイルを確立しつつあります。
(2025年当社インターネット調べ)
________________________________________
■ AISASモデルとは? 学生の行動プロセスを可視化する
AISASモデルは、デジタル時代の消費行動を表すマーケティング理論です。
以下の5つのステップで構成されています:
Interest(関心):その内容に“興味を持つ”
Search(検索):自ら調べて“情報を深める”
Action(行動):購入・応募・資料請求など“行動に移す”
Share(共有):SNS・就職情報サイトなどで“情報を拡散する”
この流れを学生に当てはめると、デジタルサイネージと、SNS・就職情報サイト等の役割が明確になります。
1.Attention・Interestはキャンパスメディアが担う
まず、AISASの最初の2段階——Attention(注意)とInterest(関心)。
ここを担うのが、大学内に設置された「キャンパスメディア(学食・購買・ラウンジモニター)」です。
- 学食モニター:日常の中で確実に“目に入る”
学生の多くが昼休みに必ず立ち寄る学食は、大学内で最も滞在時間が長い場所。配膳カウンターやテーブル前に設置されたモニターで広告を放映すれば、強制的ではなく自然な形で視認される環境をつくれます。映像と音声を活用した広告は、ポスターやバナーよりも高い印象効果を持ち、学生の興味を引き出します。
- 購買モニター:行動直前のAttention
購買エリアでは、学生が文房具や軽食を選ぶ“購買モード”の瞬間に広告が流れます。購買行動と広告接触がリンクすることで、「この商品見たことある」という購買心理を生み、記憶に残りやすくなります。
SNS・就職情報サイト広告では難しい“現場体験に紐づいた興味喚起”が可能です。
- ラウンジモニター:静かな空間で深いInterestを育む
談話スペースや自習ラウンジに設置されたモニターでは、学生がリラックスしている時間帯に広告が届きます。企業のブランドストーリーや採用動画を流すことで、「共感」や「憧れ」を醸成し、学生の関心を長期的に高めます。
このようにキャンパスメディアは、学生の日常のなかで“自然に注意を惹き、興味を持たせる”という重要な役割を果たします。
2. Search・Action・ShareはSNS・就職情報サイトやWEB広告が担う
次の段階、Search(検索)・Action(行動)・Share(共有)は、SNS・就職情報サイトの得意領域です。キャンパスメディアでAttentionとInterestを獲得した学生は、気になった企業名や商品をスマートフォンで検索します。QRコード等を広告に組み込めば、ワンクリックで公式サイト・採用ページ・キャンペーンページに誘導することも可能です。
- Search:興味を深める導線設計
学生はスマホ検索で企業のSNS・就職情報サイトや採用サイトを閲覧し、詳細情報をチェックします。大学広告によって「初めて知った企業」を深掘りするきっかけを与えることで、自然な流入が生まれます。
- Action:行動を促すオンライン施策
SNS・就職情報サイト広告やリターゲティング広告を組み合わせることで、キャンパスメディアで接触した学生に再度アプローチが可能です。「エントリー」「説明会予約」「資料請求」などの具体的行動を促すのは、このデジタルフェーズの役割です。
- Share:学生が拡散する“信頼の輪”
学生は興味を持った情報をSNS・就職情報サイトで共有する傾向があります。実際にキャンパスモニターで見た広告を「学食で流れてた!」「この会社の動画おもしろい」と投稿するケースも少なくありません。また、視聴者の内21.28%は友人と情報共有をしたというアンケート結果も出ています。リアル体験とオンライン拡散の融合が、ブランドの信頼性を高める連鎖を生み出します。
3. キャンパスメディア×SNS・就職情報サイトの連動が生む“多層的なリーチ”
AISASにおける役割分担を理解すると、キャンパスメディアとSNS・就職情報サイトの相乗効果が明確になります。キャンパスメディアは学生の生活空間における「最初の接点」、SNS・就職情報サイトはその後の「行動と拡散の場」。両者を組み合わせることで、広告効果は一気に高まります。
4.SNS・就職情報サイトでは得られない「信頼」「記憶」「共感」
SNS・就職情報サイト広告は拡散力に優れますが、同時に「一瞬で流れてしまう」という弱点もあります。
一方、キャンパスメディアは“生活のリズムに沿った広告接触”が可能です。毎日目にする環境だからこそ、学生の潜在意識に刷り込まれ、「なんとなく覚えている」「見たことある」というブランド記憶を形成します。
特に採用広報においては、この“リアルな接触”が信頼を生み、学生が自ら調べて応募する行動につながります。オンライン広告では作れない「親近感」と「安心感」が大学広告の真価です。
________________________________________
■ 大学広告の費用感と出稿までの流れ
大学広告は、媒体・期間・大学規模によって異なりますが、1キャンパスあたり数万円~十数万円で出稿可能です。動画・静止画の制作、掲出申請、掲載期間の調整など、長田広告が一括サポート。全国の大学と直接提携しているため、スムーズかつ確実な運用が可能です。
出稿の流れは次の通りです。
1.目的ヒアリング(採用/商品/ブランド訴求)
どのような学生に、何をどのように伝えたいのかを、ヒアリングを通じて共有します。
2.ターゲット大学・媒体選定(学食/購買/ラウンジ)
エリア・学生属性・訴求内容に合わせて、学食・購買・ラウンジなど最適な媒体と大学を選定します。
3.素材制作・掲出申請
動画や静止画の制作、掲出許可の申請、スケジュール調整などを一括でサポート。デザインから運用まで安心対応。
4.放映開始・レポート提出
放映開始後は、放映状況や反応データをレポートとして提出。効果検証や次回施策への改善提案も行います。
キャンペーン期間中の素材差し替えや複数大学同時出稿も柔軟に対応可能。
初めての方でも、担当者が大学側との調整まで代行するため、安心して導入できます。
________________________________________
■ まとめ:大学広告で、未来の人材・顧客と出会う
「大学広告」は、単なる掲出メディアではなく、学生と企業をつなぐプラットフォームです。
学食・購買・ラウンジという日常空間に自然に溶け込みながら、ブランドの存在を印象づけ、学生の行動変容を促します。
長田広告のキャンパスメディアは、大学別に設計された最適な放映環境と全国ネットワークで、採用・商品・地域連携などあらゆる目的に対応。学生への“リアルなリーチ”を求める企業の皆様に、確かな成果をお届けします。
今すぐ「キャンパスメディア媒体資料」をダウンロードし、自社の課題解決につながる最適なキャンパス広告プランを検討してみませんか?
キャンパスメディアWEBページ:https://ad-nagata.com/services/campus-media
キャンパスメディア資料請求:https://ad-nagata.com/documents/campusmedia-mediaguide